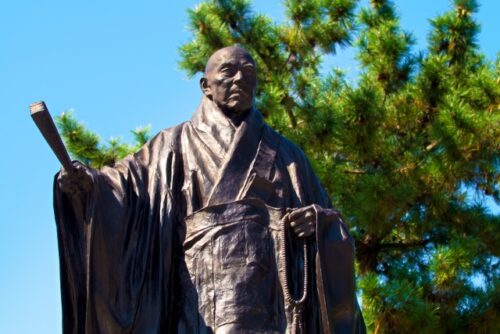織田信長の性格と人柄とは?歴史やエピソードを交えて徹底解説

織田信長のイメージは独裁者のイメージが強く思われているでしょう。確かに自己中心的なところもあります。しかし必ずしもそうとは限らないところもあります。そこで信長の人柄や性格などを徹底解説します。
目次
織田信長の人柄で伝えられているエピソード
織田信長の人柄で伝えられているエピソードは
- 尾張の大うつけ者だった。
- 恵まれて発想力・改革のある人物だった
- 身分に関係なく能力のある者は高い地位を与えた
- 残虐非道な行いもしていた
の4つです。ここから一つずつ解説します。
尾張の大うつけ者だった
<うつけ者とは、中身がしっかりしていない人・常識外れなどの意味です>
子供の頃から家臣に冷ややかな目で見られていた。なぜなら、織田家後継者らしからぬ行動をしていたからです。
◍侍らしからぬ変わった服装をしていた。
◍人目を気にせずモノを食べ歩きする
◍民と同じように町の若者と戯れる(遊びあるく)
などの礼儀作法に欠けていた行動をしていたため、将来を不安視されていました。
恵まれた発想力・改革のある人物だった
当時は生きるか死ぬかの戦国時代。そんな世の中でありながら、信長は斬新な発想力と改革を多く行っています。
大規模な街道整備
道を広くまっすぐにして、川に橋をかける。関所の廃止。一定間隔で飲食店を設置。これにより街道の治安向上や人の往来が容易になり、商業が活性化して税収も増えた。
自由取引市場を作る
城下町は、今まであった「独占販売権」「非課税権」「不入権」などの特権を持つ市座・問屋などを排除して、自由に取引市場ができる「楽市楽座」を作り、通行税もないためたくさんの物資が流通し、貿易を行ったことで経済をより活性化させた。
兵農分離を行った
通常、戦が起きたとき農民は戦に駆り出されていた。そのため農作業を中断することになるので、田植えや稲刈りに苦労しているのが当たり前のことでした。しかし信長は農民を戦に駆り出すことをしないように、プロの軍隊(軍人)を組織を作りました。
このような発想と改革ができるのも、生まれ持った才能と子供の頃から民と関りがあったからできたのかもしれません。
身分に関係なく能力ある者は高い地位を与えた
能力がある人材に対しては、身分に関係なく高い地位を与えていました。
その中でも有名なのが、足軽から始まり戦を重ねるたびに出世したのが秀吉です。また光秀も途中から家臣になったにも関わらず、坦々と物事を進めることから異例のスピード出世をしています。
これらのことから信長と言う人は、いち早く才能を見抜く力があったのかもしれません。
残虐非道な行いもしていた
信長は裏切られた人物には、一部の例外を除き厳しく追及し処罰をしています。
そして皆さんが知っている比叡山焼き討ち。他にも百済寺の焼き討ちや法華宗と浄土宗の宗論では、挑戦的な態度を取る法華宗に対して弾圧を行っています。
神も仏も怖いもの知らずなところが信長らしいとも言えるでしょう。
織田信長の性格エピソードは?
信長の性格の性格で後世に伝えられているのは
- 自己中心的な性格
- 徹底した合理主義者
- 意外と優しい心を持っていた
この3つがエピソードとして残されています。では一つずつ解説します。
自己中心的な性格
他国の大名たちは、政策や方針を決めるときは必ず会議を開き、話し合いで物事を決めていましたが、信長は回りの意見を聞かず、すべて自分で決めるワンマン経営でした。
でも的外れではなくほとんどが成功を収めていることが不思議なところです。そのためか家臣たちは信長から離れることはなかった。ただ怖いからとの理由などで、離れることができなかった家臣たちもいたようです。
徹底した合理主義者
何事にも理性的として割り切って物事の処理をしていた。特に情報収集力や活用力に長けていたのが信長です。
例えば、戦で成功を収めた人や正確な情報を得て成功した人には褒美を与える。逆に失敗した人には厳しい処分をしていました。また中には切腹を言い渡される人もいたそうです。今で言う仕事人間で、鬼上司みたいな性格だったと思わります。
意外と優しい心を持っていた
天下人として公の場では、厳し信長でしたが、私生活や忠実な家臣には優しいところがあったと伝えられています。
- 秀吉と寧々の夫婦喧嘩の仲裁に入った。
- 尾張に妻子を残し戦に出た家臣たちには気持ちをしっかりさせるために叱責した。
- 信長には娘が多くそのため嫁ぎ先に苦楽を共の過ごしてきた家臣の妻にしている。
- 正室・側室問わず女性に対しては優しく接していた。
このことは諸説ありますが、信長にも人を思いやる一面があったということです。
宣教師ルイス・フロイスが見た信長のエピソード

宣教師として訪れていたルイス・フロイスが、日本の様子を母国に報告するために、書いた記述の中に、織田信長の人柄や性格などのエピソードが書かれていました。その内容とは、
- 「喜怒哀楽」のある人物ですが、普段は大人しい人だった。
- 戦を好み、修練に励み、曲がったことが嫌いな厳格な人である。
- 家臣の言う事は聞かず、己の道を突き進む人。
- 神仏(宗教)的なことは、否定的であった。
- 人情味のある行動を示すこともあった。
- 家臣の身分に関係なく親しく話をする。
などのことや戦場で大胆な行動をしたり、厳しい戦でも機転の利く戦術をしたりと、信長に対して才能豊かな魅力ある人物として、見ていたようです。
なぜ天下統一を目指したのか?
信長が生きた戦国時代は、生きるか死ぬかの綱渡りの世の中とも言えるでしょう。信長自身も戦に明け暮れ、領地を広げるために残虐な行為もしました。
そして政略結婚も当たり前。また幕府の権力が失墜している中で、新しい将軍を擁立させ、自分は将軍の次に権力があると諸国大名に示しています。
ここまでくると、信長は権力が欲しいがために動いているように思いますが、別の解釈もあるようです。
本当は戦のない、民が平穏な生活ができるように、したかったのではないのかということです。
戦が起きればなんの罪のない民が犠牲を払うことが多かったため、天下統一を成し遂げれば、民はもちろんのこと、諸国大名や家臣たちも、安泰に暮らせるのではと考えていたとも言われています。
本能寺でおきた信長最後の出来事
信長を語る上で外すことができないのが「本能寺の変」です。実際に明智光秀の配下として従軍していた兵士、本条惣右衛門が書き残した覚書から、解説します。
光秀の軍勢は毛利攻めに向かっていましたが、突如京都方向へ進軍したため、毛利攻めではなく、徳川家康を討つのだと惣右衛門は思ったそうです。
なぜ家康を討つと思ったのかはわかってはいませんが、織田家と徳川家で険悪な関係になっていたのかもしれません。
本能寺に着き、門番の首を取り、また門は簡単に開き、中は静寂な様子で、襲撃されていることも気づかない状態だったとのことです。
そして本堂には家臣は一人もおらず、女性を捕らえ「上様は白い着物を着ています」と信長の身なりを聞いていました。その時は上様が信長だとは分かっていませんでした。
その後明智勢は何人かの首を取り、惣右衛門も一人の首を取ったことで、褒美に槍を貰いましたと記述はそこで終わっています。
結局のところ、信長の最後の記述がないため、正確なことは分かりませんが、発掘調査で本能寺が焼けた形跡があることから、火をつけたのは事実だと思われますが、惣右衛門の覚書からは、テレビなどで見る攻防戦はなかったようです。
まとめ:織田信長の人柄・性格は自己中心的であった
信長について諸説ありますが、正確なことは今も分かっていません。ですが公の場では、厳しく自己中心的な部分はあったと思われます。
その反面人情深い気持ちもあったようです。でも明智光秀のように、家臣たちの中には、信長に不満をもっている人もいたのは事実です。
家臣にそのように思われていることは、傲慢な部分があり、信長自身が招いた結果なのでしょう。