平清盛はどんな人?政治や年表も含め解説【鎌倉殿の13人】第8弾
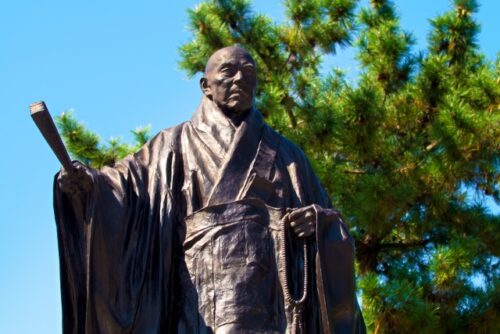
平清盛が生まれたときは、貴族が勢力のある時代で、武家は低い立場にいました。
しかし、貴族の力が衰退し、武家も次第に力をつけていき、貴族をも越え最高権力者となったのが平清盛です。
「平家物語」でも記されている、時代の転換期に生きた清盛は、どのよう人なのか、また権力を得てどのような政治を行ったのかを、解説していきます。
目次
平清盛はどんな人なのか
平清盛はドラマなどでは、悪人のイメージが強いでしょう。
ですが、あまり描かれていない、家庭環境や意外な一面もありました。
その具体的なことは、
- 生誕から訳ありな人だった
- 天皇家の外戚(がいせき)になる
- 清盛の性格は?
この3つについて解説します。
生誕から訳ありな人だった
平清盛は、永久6年1月18日(1118年2月10日)に、伊勢平氏の棟梁(とうりょう)である平忠盛の嫡男として生まれ、出身地は諸説ありますが、山城国・京(現在の京都市)が有力です。
母は白河法皇に仕えていた女官・祇園女御(ぎおんのにょうご)が、忠盛へ嫁いだと言われています。
ただ一説によれば、祇園女御は白河法皇の寵愛を受けていて、忠盛に嫁いだ時は懐妊しており、その生まれた子が清盛で、いわゆる「ご落胤説(ごらくいんせつ)」です。
他にも、生母は祇園女御の妹で、養子ではないかという説もあり、清盛は生まれた時点から、訳ありで波瀾万丈なのかもしれません。
🖋〖棟梁(とうりょう〗一族・一門の統率者。また、一国を支える重職。
🖋〖ご落胤(ごらくいん)〗身分の高い男が、正妻以外の身分の低い女に、生ませた子。
天皇家の外戚(がいせき)になる

平清盛は自分の娘を高倉天皇に嫁がせて、生まれた子・安徳天皇が即位し天皇の外戚となり、当時の常識的な風習と、親戚の立場を利用して「摂関政治(せっかんせいじ)」を行い、権力を強めていきます。
「摂関政治」は、平安時代では当たり前であった、妻の実家が子供の後見役となり、清盛は天皇の義理の祖父となり、見事なまでの根回しで、政治の実権を握ったのです。
🖋〖外戚(がいせき)〗天皇の母方の一族を言います。
清盛の性格は?
平清盛は「平家物語」では、悪人要素たっぷりの独裁者として書かれています。
ですが実際は、相手が下僕(げぼく)であっても、一人前の人物として扱う、情のある優しい一面がありました。
また、平治の乱の後に、源義朝の子供たちを処刑せず、流刑にしていることを考えると、清盛は情け深い性格だったことが伺えます。
しかし、この判断がのちに、災いをもたらすことになるとは、思ってもいなかったのでは、ないでしょうか。
🖋〖下僕(げぼく)〗召使いの男。下男。しもべ。
平清盛は何をした人なのか
平清盛は皇室の内乱を上手く利用して、貴族よりも実力があると見せつけました。
そうして得た権力を使い、政治面や貿易などに力を注いでいきます。
では実際、何をしたのか?
- 保元の乱と平治の乱
- 武家として始めて太政大臣になる
- 日栄貿易と厳島神社の整備
これら3つについて解説します。
保元の乱(ほうげんのらん)と平治の乱(へいじのらん)
「保元の乱」は、1156年京都で起きた内乱です。
皇室では崇徳上皇(すとくじょうこう)か後白河天皇(ごしらかわてんのう)かの皇位継承問題が起き、平清盛は源義朝(みなもとのよしとも)と共に軍を率いて、後白河天皇に付き見事勝利し、崇徳上皇は讃岐(現・香川県)に流されました。
この事件で、貴族の無力化と武士の実力を見せつけ、武士政治へのキッカケの一つになります。
「平治の乱」は、1159年にまたも京都で起きた内乱です。
保元の乱のあと、藤原通憲(ふじわらのみちのり)が権勢を振る舞い、源義朝ともに不満を持つ勢力とが組み、反乱を起します。
この乱も武士である平氏の力を借りて、源氏の棟梁である源義朝は戦死し、その息子であった源頼朝も伊豆に流され、源氏は壊滅的な打撃を受けることになりました。
🖋【藤原通憲】は、雅仁親王(後白河天皇)の養育係兼側近。
武家として始めて太政大臣になる

平清盛は「保元の乱」「平治の乱」と自らの地位を盤石にして、更には、妹や娘を皇室と摂関家(せっかんけ)に嫁入りさせたりと、急速に勢力を拡大し朝廷での権威(けんい)を強めていきます。
そして1167年に、貴族のトップとも言える地位である「太政大臣」に任命され、武家としてだけでなく公家としての栄華も極めたことになりました。
ちなみに、平氏による政権は、平家一門が住んでいた六波羅だっだことから「六波羅(ろくはら)政権」とも呼ばれています。
🖋【摂関家(せっかんけ)】摂政・関白に任ぜられる家柄。
🖋【太政大臣(だじょうだいじん)】律令制で、太政官の最高の官。筆頭長官。
🖋【六波羅(ろくはら)政権】京の居館があった地名から取った政権名。
日栄貿易と厳島神社の整備

平清盛は、平氏繁栄のために「日栄貿易」に力を注ぎ、かなりな富を得ていたようです。
日宋貿易は日本と中国の宋(南宋)との間で行われた貿易で、日本からは金銀や銅が輸出され、宋から宋銭や中国製の陶磁器、絹織物などが輸入されていました。
また、宋との貿易の効率を高めるため、瀬戸内海の航路を整え、宋船が入港しやすいように、大輪田泊(現・神戸港)を整備しています。
また清盛は院政時代の文化も大切にしていました。
特に「厳島神社」への信仰が深く、豪華な平家納経を納めたり、厳島神社を寝殿造り(しんでんづくり)に大改修したのも清盛です。
現在は、世界でも珍しい海上社殿造りで、世界遺産として登録されています。
🖋【寝殿】平安中期に成立した貴族の住宅形式。
平清盛の年表
| 西暦(年齢) | 出来事 |
| 1118年(0歳) | 平忠盛の嫡子(長男)として生まれる。 |
| 1129年(12歳) | 従五位下に任ぜられる。 |
| 1132年(15歳) | 父・忠盛が武士として、初めて昇殿を許される。 |
| 1135年(18歳) | 父・忠盛の西国海賊追討の恩賞の譲りで、従四位下を任ぜられる。 |
| 1137年(20歳) | 父・忠盛が熊野本宮を造営した功により、清盛は肥後守を任ぜられる。 |
| 1138年(21歳) | 高階基章(たかしなもとあき)の娘と結婚するが死別。 その後、平時子と再婚。 |
| 1146年(29歳) | 安芸守を任せられ、瀬戸内の制海権を得る。 |
| 1147年(30歳) | 祇園社で闘乱事件を起こす。 |
| 1153年(36歳) | 父・忠盛死去し、平氏の棟梁を継ぐ。 |
| 1156年(39歳) | 保元の乱 勃発し、後白河天皇側につき源義朝とともに源為義、平忠正らを討つ。 勲功賞で播磨守を任じられる。 |
| 1159年(42歳) | 平治の乱 勃発し、源義朝と戦い勝利。武士の王となる。 |
| 1160年(43歳) | 後白河上皇に命じられ、新熊野神社を造営。 |
| 1161年(44歳) | 中納言に任ぜられる。 後白河上皇に嫁いだ妻の妹・滋子が、皇子(高倉天皇)を生む。 |
| 1167年(50歳) | 太政大臣を任じられるが、3か月で辞任。 |
| 1168年(51歳) | 熱病に苦しめられる。 その後、出家し厳島神社を大規模に造営する。 |
| 1169年(52歳) | 福原(現・神戸)に別荘を造り居住する。 |
| 1170年(53歳) | 後白河法皇を福原に迎え、中国・宋の特使と面会する。 |
| 1173年(56歳) | 大輪田泊に人工島・経が島(きょうがしま)竣工する。 |
| 1177年(60歳) | 鹿ヶ谷の陰謀 発覚 平家に対立する院近臣を一掃し、後白河法皇との対立が深刻化。 |
| 1179年(62歳) | 長男・重盛死去。 清盛、後白河法皇を幽閉、院政を停止する。 |
| 1180年(63歳) | 京都から福原への遷都を断行するが、6か月で還都する。 源頼朝が伊豆で挙兵。富士川の戦いで平家軍敗走。 |
| 1181年(64歳) | 熱病に倒れ死去。 |
平清盛に関するQ&A
今回のQ&Aは、平清盛の人物像が良くわかるポイントとして
- 女性に目がなかった
- 平清盛の晩年
この2つについて解説します。
女性に目がなかった
平清盛は、綺麗な女性に目がなかったと言われています。
祇王(ぎおう)・祇女(ぎじょ)という、歌や舞を披露する白拍子(しらびょうし)の姉妹を、寵愛していましたが、新たに仏御前(ほとけごぜん)が現れて、綺麗な白拍子の舞を見て気に入ってしまい、側におくために、祇王と祇女の姉妹を追い出したのです。
姉妹は出家し仏門に入りましたが、そこに仏御前が訪ねてきて、2人を追い出した清盛のような人の世話になりたくないと、仏御前も同じく出家してしまいました。
また、源義朝の側室であった常盤御前を強引に妾(めかけ)にしたという話もあり、自分の利益になるための婚姻などが多い中、清盛はただの女好きだったと言えるでしょう。
平清盛の晩年

平清盛の晩年は、一気に勢いが衰退しています。
その大きな要因は、後白河法皇の正妻だった平滋子の死でした。
後白河法皇と平清盛は、互いに権力持ちたいがために対立関係にありましたが、大きな争いが起きなかったのは、両者の力関係を理解し、陰で支えていた平滋子がいたからです。
しかし、彼女が亡くなった事で、対立が表面化して起きた事件が「鹿ケ谷の陰謀(ししがだにのいんぼう)です。
また1179年に、平清盛と後白河法皇との間に所領を巡る争いが勃発し、後白河法皇を脅し、幽閉した事件が「治承三年の政変」です。
また、清盛は1180年に孫を安徳天皇として即位させました。
本来、即位決定権は法皇が持っていますが、後白河法皇は幽閉中なので、清盛が勝手に即位させてしまいます。
こうした独裁政権をしたことで、次第に周りからは不満が多くなりました。
🖋【鹿ケ谷の陰謀】1177年に平清盛がでっち上げた事件。後白河法皇の近臣を失脚し、朝廷での影響 力を失わせた。
まとめ:平清盛は権力に取りつかれた事で自滅してしまいました
平清盛は初の武士中心の世の中を作り上げました。
平家一族の繁栄を築き、貿易にとりくみ、厳島神社の改修など社会貢献もしましたが、自分や一族にとって思いのままの政治を行った事で、様々な人たちが不満を持ち味方が敵に変わり、自滅する道を進んでしまいます。
ただ平家滅亡を知らず、亡くなったことが、唯一の救いだったかもしれません。


